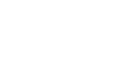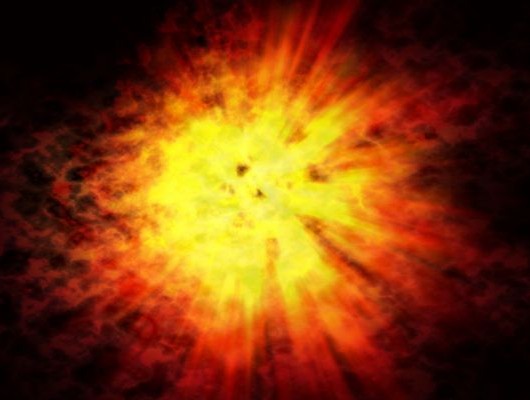火災を発生させない対策について
日本国内工場等の火災件数は年間約2,000件と推定されており、製造業の現場において深刻なリスクとなっています。近年は件数こそ減少傾向にあるものの、設備の老朽化や新素材の導入、作業環境の複雑化により、火災の原因は多様化しています。

主な出火原因としては、電気設備の不具合(漏電・過負荷・配線の劣化)、溶接作業中の火花、ガス・石油器具の過熱や漏れ、可燃性粉塵による爆発などが挙げられます。
クリックして読む⇒工場・機械における過熱火災の要因
火災による損失は、設備や製品だけでなく、従業員の安全、企業の信用、地域社会への影響にも直結します。火災を「発生してから対処する」のではなく、「発生する前に予兆を捉えて防ぐ」対策が極めて重要です。
クリックして読む⇒火災防止と早期発見の実践的アプローチ
工場・機械における過熱火災の要因
工場や機械の代表的な火災要因を以下に挙げます。 参考資料:工場で使われる物質・材料の発火関連温度
- 潤滑不良 参考資料:機械の通常運転時の表面温度
⇒ ベアリングやギアの油切れが原因で摩擦熱で100℃超えると発火リスク - ほこり・粉塵 参考資料:粉じんの発火関連温度
⇒ 機器表面に積もると自己発火温度(AIT※)より低い温度で発火 - モーターの絶縁劣化
⇒ コイル温度上昇による絶縁材炭化・発煙 - 古い配線・接点不良
⇒ 接触抵抗の発熱で局部的に200℃以上になることも - 冷却不良
⇒ ファン故障・ファンの目詰まりで熱がこもる
※自己発火温度(AIT)------物質が空気中で自然に発火する最低温度
過熱の原因
過電流

金属疲労

摩擦増大
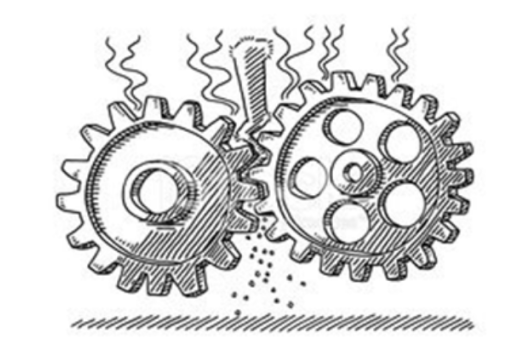
受軸損傷

老朽化
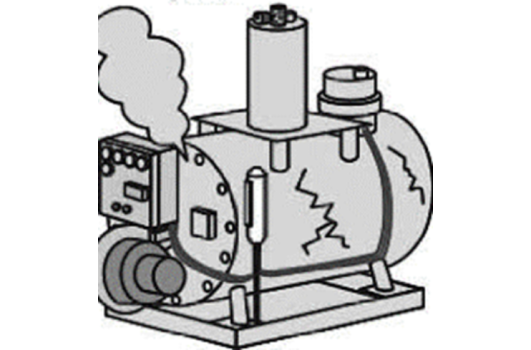
異常振動

高調波

グリス切れ

放熱不良

火災防止と早期発見の実践的アプローチ
火災の要因を踏まえた上で、一般的な対策方法について説明します。
- 温度監視(一次防衛) 参考資料:機械の通常運転時の表面温度
・温度センサーを主要部(モーター筐体、ベアリング、オイル槽)に設置
・サーモグラフィーカメラを定期点検に導入してホットスポットの可視化 - 電流・振動監視(異常の予兆)
・モーター過電流の監視で過熱の前兆を検知
・ベアリング振動で潤滑不足は摩耗の兆候を検知 - しきい値(警報温度)の設定 参考資料:物質・材料の推奨警報設定温度
・正常運転時+20~30℃を注意レベル
・90℃超えを警報レベル
・120度越えを緊急停止レベル(一般機械の目安) - 環境管理 参考資料:粉じんの発火関連温度
・定期清掃で粉じんの堆積防止
・配線・電気盤の赤外線点検
・換気・強制冷却ファン追加で温度上昇を抑える - 記録・傾向監視
・温度データを記録し、トレンド異常(徐々に上昇する傾向)を検出
・長期間の監視で「傾向把握」して過熱の早期発見
このような背景から、ぜひご検討いただきたいのが「過熱火災監視システム」です。このシステムは、工場設備や機械の過熱状態をリアルタイムで監視し、火災の前兆を早期に検知することで、未然に火災を防ぎます。最大2,000点の温度計測が可能で、多点温度の一元管理や耐ノイズ性に優れた情報伝送技術「ユニバーサルライン」を採用しており、劣悪な環境下でも安定した監視が可能です。また、既存設備への後付けも容易で、省配線・省施工・省スペースを実現しています。
過熱火災監視システムについて漫画で紹介しています。画像をクリックするとお読みいただけます。
▼下記をクリックしてご覧ください(PDF)▼

参考資料
過熱監視の情報(発火温度・発熱温度等)について
工場で使われる物質・材料の発火関連温度(一般目安)
・「推奨警報設定温度」は自己発火温度(AIT)から100~150℃程度の余裕を持たせた値を目安にしています。
・3段階の警報設定温度(注意・警報・停止)を設けることで早期検知につながります。
注意→様子見・監視強化 / 警報→負荷低減・現場点検 / 停止→強制停止・安全側動作
・自己発火温度(AIT、Auto Ignition Temperature)
定義:外部の発火源がなくても、物質が空気中で自然に発火する最低温度。
| 区分 | 物質・材質 | 自己発火温度(AIT) 目安 | 推奨警報設定温度 目安 |
|---|---|---|---|
| 潤滑油 | 鉱物系潤滑油 | 約365℃ | 注意:200℃ 警報:230℃ 停止:250℃ |
| 燃料 | ガソリン | 約280℃ | 注意:150℃ 警報:180℃ 停止:200℃ |
| 燃料 | 軽油 | 約210℃ | 注意:120℃ 警報:150℃ 停止:170℃ |
| 燃料 | 灯油(ケロシン) | 約210~220℃ | 注意:120℃ 警報:150℃ 停止:170℃ |
| 溶剤 | エタノール | 約365℃ | 注意:180℃ 警報:200℃ 停止:220℃ |
| 溶剤 | イソプロパノール(IPA) | 約455℃ | 注意:200℃ 警報:230℃ 停止:250℃ |
| 溶剤 | アセトン | 約465℃ | 注意:200℃ 警報:230℃ 停止:250℃ |
| ポリマー | ポリエチレン(PE) | 約330~410℃ | 注意:150℃ 警報:180℃ 停止:200℃ |
| ポリマー | ポリ塩化ビニル(PVC) | 約500℃ | 注意:200℃ 警報:230℃ 停止:250℃ |
| エラストマー | ニトリルゴム(NBR) | 約313~500℃ | 注意:150℃ 警報:180℃ 停止:200℃ |
| エラストマー | 天然ゴム | 約250~330℃ | 注意:120℃ 警報:150℃ 停止:170℃ |
| 紙・段ボール | 紙 | 約230℃ | 注意:110℃ 警報:130℃ 停止:150℃ |
| 木材 | 木材(一般) | 約300~500℃ | 注意:150℃ 警報:180℃ 停止:200℃ |
| コンベア材 | ゴム/PEベルト | 約300~410℃ | 注意:150℃ 警報:180℃ 停止:200℃ |
| コンベア材 | PVCベルト | 約500℃ | 注意:200℃ 警報:230℃ 停止:250℃ |
| モーター周辺 | 絶縁ワニス・樹脂 | 多くは約300℃以上 | 注意:150℃ 警報:180℃ 停止:200℃ |
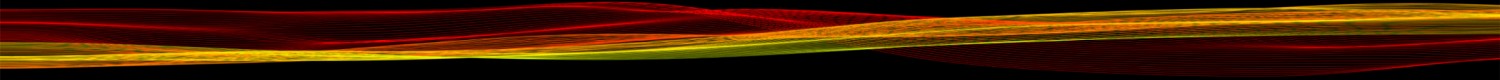
粉じんの発火関連温度(一般目安)
粉じん設備では、表面温度が自己発火温度(AIL)や粉じん層発火温度(LIT)に近づかないように「2/3ルール」と「-75Kルール」で安全値を算出します。
粉じん層発火温度(LIT、Layer Ignition Temperature)
定義:可燃性粉じんが「堆積層」として積み重なった状態で発火する最低温度です。
重要な特徴:粉じん層は粉じん雲の自己発火温度(AIT)よりも低い温度で発火します。粉じん暴発防止では粉じん層発火温度(LIT)が重要視されます。
例:小麦粉の粉じん雲のAITは約410℃だが、堆積層(5mm厚)のLITは300℃以下で発火の可能性があります。
設備表面温度との関係
モーターやベアリング、コンベアの金属表面がAITやLITに近い温度まで上昇すると発火源になり得ます。国際規格(IEC.ATEXなど)では、表面温度は粉じん雲のAITの2/3以下、表面温度はLITより75K(約75℃)低い値を超えないように設定することが推奨されています。
| 粉じん種別 | 粉じん雲発火温度(MIT) | 粉じん層発火温度(LIT) | 推奨設備表面上昇温度上限 (Tmax) |
|---|---|---|---|
| 小麦粉 | 410~430℃ | <300℃ | MITの2/3=270℃ LIT-75K=220℃ |
| でん粉(とうもころし) | 410~450℃ | <300℃ | MITの2/3=270℃ LIT-75K=220℃ |
| ゴム粉 | 約500℃ | ー | Tmax=330℃ |
| プラスチック粉 | 約430℃ | ー | Tmax=280℃ |
| アルミ粉 | 650~750℃ | ー | Tmax=430~500℃ |
| 石炭粉 | 400~850℃(条件依存) | 300~400℃ | Tmax=260℃/220~320℃ |
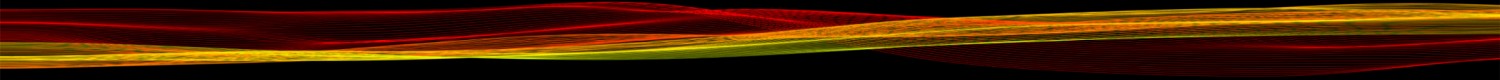
工場機械の通常運転時の表面温度(目安)
| 機械・部位 | 通常運転時の表面温度 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 電動モーター筐体 | 60~90℃ | モーター絶縁クラスで規定あり(例:クラスFは巻線温度155℃まで許容、外装はそれ以下) |
| 受け軸(ベアリング)外周 | 50~90℃ | 政情は60℃以下、90℃を超えると異常摩擦や潤滑不良の可能性 |
| ギアボックス外装 | 60~80℃ | 負荷が高いと100℃近くなる場合あり |
| コンベアローラー表面 | 40~70℃ | 摩擦増大で90℃を超えると危険信号 |
| ポンプ・ファン筐体 | 40~80℃ | 流体温度や摩擦によって上昇 |
| 圧縮機(コンプレッサ)外装 | 80~120℃ | 圧縮比が高いと出口部はさらに高温に |
| 蒸気配管・ボイラ外装 | 150~200℃(断熱なし) | 断熱材があれば外装は60℃前後 |
| 潤滑油層・オイルバス | 50~80℃ | 劣化防止のため通常は80℃以下に管理 |
関連ページ
(3010)